2008年06月01日
安岡正篤 珠玉の言葉
母についての一節
世に母の徳はど尊く懐かしいものはあるまい。母は子を産み、子を育て、子を教え、苦しみをいとわず、与えて報いを思わず、子と共に憂い、子と共に喜び、我あるを知らぬ。
夫に添うては夫を立て、夫の陰に隠れて己の力を尽くし、夫の成功をもってみずから満足している。
夫や子が世間に出て浮世の荒波と戦っている時、これに不断の慰謝(なぐさめ)と奮励とを与える者は母である。夫や子が瞋恚(いかり)の炎に燃え、人生の不如意を嘆ずる時、静かな諦観と久遠の平和とに導くのも母である。と結ばれている。
我々男性にとって父の日が近いのだがあまり深く考えずにおこう。母は尊いのだから。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
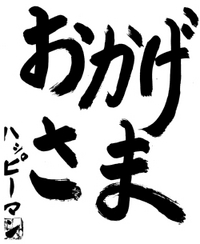
世に母の徳はど尊く懐かしいものはあるまい。母は子を産み、子を育て、子を教え、苦しみをいとわず、与えて報いを思わず、子と共に憂い、子と共に喜び、我あるを知らぬ。
夫に添うては夫を立て、夫の陰に隠れて己の力を尽くし、夫の成功をもってみずから満足している。
夫や子が世間に出て浮世の荒波と戦っている時、これに不断の慰謝(なぐさめ)と奮励とを与える者は母である。夫や子が瞋恚(いかり)の炎に燃え、人生の不如意を嘆ずる時、静かな諦観と久遠の平和とに導くのも母である。と結ばれている。
我々男性にとって父の日が近いのだがあまり深く考えずにおこう。母は尊いのだから。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
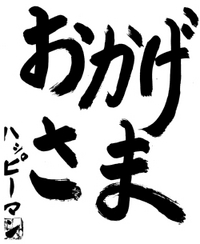
Posted by おかげさま at
16:59
│Comments(0)
2008年06月01日
母取其愛。6
昭和28年私が12才になった頃、父は長年勤めた会社を定年退職になってふるさと熊本に帰る予定だったのですが、病に倒れて約1年間病院で過ごし帰ってきました。やっと親子3人水入らずの生活がここから始まりました。我が家は戦前に建てられ、納屋を改造した建物だったので家屋敷を近所の方に譲って、近くの町に家を建て引っ越しました。そこでは古物商の許可を受けて古着屋さんを始めました。当時の古着といえば国鉄や郵政省の職員さんが着ていた制服で品質がよくて工場で働く人や農家で働く人に喜ばれ、よく売れました。母は父と私の2人を支えるために文句も、泣き言も言わず頑張ってくれました。私が手伝い出来たのは夏休みと冬休みぐらいでほとんど母が働いています。私は高校を卒業と同時に大阪へ就職して現在に至っていますが、母が入院生活を始めたとき手紙が届きました。そこには私の体は医学のために使って頂くから反対するなといったことが書かれていました。常日頃から「社会のために」という言葉を聞かされていましたからなにも驚きませんでした。私もそうしたいと思います。
おわり。
http:www.kidsdream.co.jp/misumi/
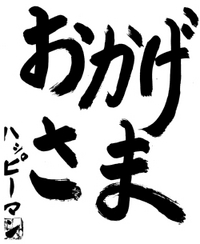
おわり。
http:www.kidsdream.co.jp/misumi/
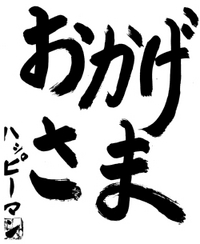
Posted by おかげさま at
15:30
│Comments(0)
2008年06月01日
母取其愛。5
昭和25年当時の子供の娯楽といえば「紙芝居」。目の前が本家で、その隣が本家が管理する「お堂さん」。天気のよい日はお堂さんの敷地で元映画の弁士だったオジサンが日曜には拍子木をたたきながら自転車でやってくるのが楽しみでした。
雨が降ると我が家の土間を貸していました。おおらかな性格の母だったから出来たのかもしれません。普通はマンガと人情物、それに時代劇ものですが子供だけでなくおとなも見に来ていました。その頃おとなの娯楽は浪曲の実演ですが、我が家はそれほど客数が入りきれないので農家のぶち抜き20畳ぐらいを提供してもらって演じていました。ラジオしか無い時代だったので生で聞けて「迫力」をおとなは感じたのではないでしょうか。
つづく。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
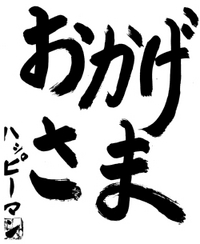
雨が降ると我が家の土間を貸していました。おおらかな性格の母だったから出来たのかもしれません。普通はマンガと人情物、それに時代劇ものですが子供だけでなくおとなも見に来ていました。その頃おとなの娯楽は浪曲の実演ですが、我が家はそれほど客数が入りきれないので農家のぶち抜き20畳ぐらいを提供してもらって演じていました。ラジオしか無い時代だったので生で聞けて「迫力」をおとなは感じたのではないでしょうか。
つづく。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
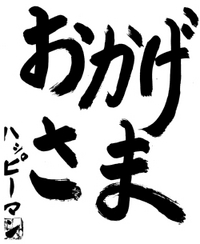
Posted by おかげさま at
12:59
│Comments(0)
2008年06月01日
母取其愛。4
母は三人姉妹の末っ子で広島の女学校を卒業と同時に東京で長女が経営する家政婦斡旋所を手伝う為に上京。そこで父と知り会い、穏田と言う所で私が誕生しました。父の田舎が熊本で、当時の東京は戦後間も無い頃で食べる事にみんなが必死だったし、会社勤めの父を残して私を連れて熊本へ疎開しました。姉妹三人とも男性的であったと聞いています。
田舎は千丁村で其の名の通り、広大な農村地帯。農作物以外に畳表の原料であるイ草の産地として栄えました。私の幼少時代は近所のあちらこちらから機織機の音が朝から晩まで聞こえていました。現在の車メーカーのトヨタはもともと豊田自動織機として生まれました。母は近所の人達と畳表(ゴザ)を集めて地方へ発送していました。現在のように車社会ではないのでリヤカーに積み込んで1キロぐらいの道のりを駅まで幾度も往復して貨車に詰め込んでいました。
つづく。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
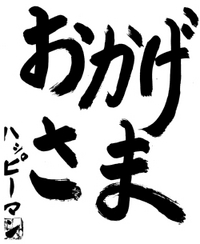
田舎は千丁村で其の名の通り、広大な農村地帯。農作物以外に畳表の原料であるイ草の産地として栄えました。私の幼少時代は近所のあちらこちらから機織機の音が朝から晩まで聞こえていました。現在の車メーカーのトヨタはもともと豊田自動織機として生まれました。母は近所の人達と畳表(ゴザ)を集めて地方へ発送していました。現在のように車社会ではないのでリヤカーに積み込んで1キロぐらいの道のりを駅まで幾度も往復して貨車に詰め込んでいました。
つづく。
http://www.kidsdream.co.jp/misumi/
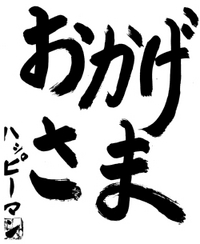
Posted by おかげさま at
11:45
│Comments(0)

